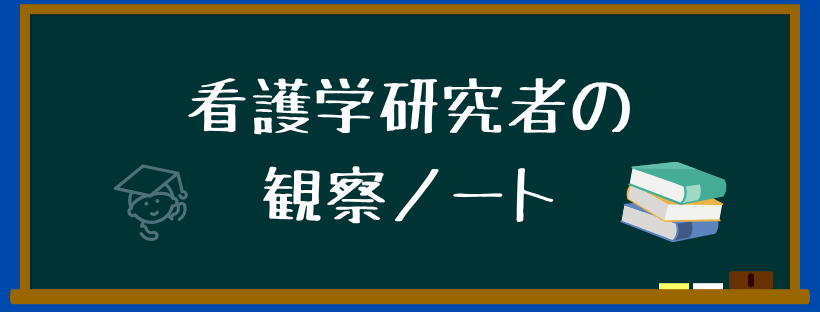自分たちの看護ケアが診療報酬に反映されない!でも実はそっちのほうが都合が良いかも?
こんにちは。東京ではツツジが咲く季節になりましたが、けっこう朝晩冷えてまだまだ起きるのがしんどい季節ですね。
臨床の看護師さんと話していると、「私たちがどれだけ患者さんにケアをしてあげてもその頑張りは診療報酬に全く反映されない。おかしい!」と話される方にけっこう出会います。気持ちはわかります。僕も看護師なので。
でもちょっと待って。私たちの看護ケアすべてに「お金」が発生したら、意外と困ることがいっぱいあるのです…!
今回はこのことについて私見を交えながら解説していこうと思います。

診療報酬の看護部分は「患者の状態に対して看護職がどのくらいいるか」
多くの看護師さんはご承知の通り、診療報酬は基本部分(入院基本料、特定入院料)と加算部分(入院基本料等加算)が基本的な部分であり、収益の多くを占める部分です。(詳しくは厚労省が出している資料がわかりやすいのでこちらを参照してください)
ここでは診療報酬に関する詳細な解説はしませんが、簡単にいうと、診療報酬において私たち看護が関係する部分の多くは「(入院患者の数や状態に応じて)看護職員がどのくらい配置されているか」ということ。つまり「どのくらいの数がいますか?」ということが問われているわけです。
ちなみに加算部分で看護職が関係する部分も、「配置されているか否か」で加算が決まるので同様です(例えば感染防止対策加算など)。
それぞれ詳しい基準を見ていくと、活動実態を伴うことが必要ですが、基本的に大前提としてはやはり「配置されているか否か」ということが重要であり、その本質的な質の部分は診療報酬には反映されていないということになります。
看護ケアの診療報酬への反映
診療の補助や療養上の世話といった、僕たち看護職の仕事の根幹をなす業務が全く診療報酬に反映されていない、というわけではありません。すでにご承知の通り、「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」というスケールで、患者の重症度と、それに応じて看護職が行うであろう診療の補助行為や療養上の世話はどの程度か、を測定し、入院基本料の基準としています。
ここで特に確認すべきは2点あります。まず1点目は、看護必要度で測定された患者状態(とそれに応じた看護職配置数)が基準となって入院基本料が決まるので、すでに僕たちの看護ケアは包括的に入院基本料に組み込まれている、ということ。2点目は、「看護必要度」で測定される項目以上の看護ケアについては診療報酬には算定されない、ということです(退院支援に関する事項や褥瘡管理加算等、別途記録や実態を伴うことで加算が得られる行為は除く)。
おそらく冒頭で紹介した方達は、この2点目のことについて言及しているのでしょう。つまり、看護必要度の項目にあがっている行為以外の看護ケアを提供しているのに反映されない、あるいは項目としてあがっている行為であっても、その回数や質は反映されない、という主張です。
(例:家族へのメンタルケアのために長時間対応している、疼痛による頻回なナースコールに対応している、点滴ラインが3本未満だが頻回に交換や薬剤注入を要している、など)
これは僕の私見を含みますが、看護必要度はあくまで入院基本料の基準をクリアしているかどうかを確認するためのスケールなので、僕たちの看護ケアすべてを評価するものではない、というのが実質的な解釈かなと思っています。
医療・看護サービスの特徴
さて、もし仮に僕たちの看護ケアすべてに報酬がついたとしたら、どのような社会になるでしょうか?
この点を考える前に、看護ケアのサービスの特徴を押さえておく必要があります。
看護ケアサービスには、いくつか特徴がありますが、ここで関係することとして「同時性」「情報の非対称性」「潜在性」を確認していきましょう。
- 「同時性」とは、さまざまなサービスが同時に提供され、提供と同時に消費される、ということです。治療というサービスと同時に、看護ケア(この場合主に診療の補助行為)が提供されます。かつ、提供されたと同時に消費されます。
- 「情報の非対称性」とは、サービスを提供する医療者側とサービスを受ける患者側で、持っている情報に偏りがあるということです。一般的なサービスの場合も多少の情報の偏りはありますが、医療サービスは顕著です。つまり、受けるかどうか選択するための情報が受け手側に不足しているので、医療者側から提示されたサービスが本当に自分にとって必要なのかどうか、判断することが難しいという特徴があります。
- 「潜在性」とは、実際にサービスを提供する場だけでなく、受け手側が認識していない場・時にもサービスが提供されている、ということです。患者さんに対面している時以外にも、退院調整を行ったり、栄養カンファレンスを行ったりと、患者さんのために直接的ではないところでサービスを提供しています。
一般的なサービスの場合、例えば飛行機に乗ったとき、CAさんに「飲み物はいかがですか?」と問われたとき、僕たちは「今は必要ありません」と拒否することが可能ですし、そのサービスを拒否したからといって、「飛行機に乗って目的地に到達する」というサービス本来の目的を得られないわけではありません。しかし医療の場合、「抗生剤を投与すべきかどうか」を患者さんのいないカンファレンスの場などで検討され、その専門的議論の場に患者さんが必ずしも同席するわけではない(潜在性)ですし、「抗生剤を点滴しますね」というサービスに対し、基本的に患者さんは拒否することは難しいのです。なぜならそれは、「治療を完遂する」というサービス本来の目的を達成できなくなります(同時性)し、それを拒否して良いのかどうかの判断を患者さん側は適切に判断することができない(情報の非対称性)ためです。
すべての看護ケア(看護サービス)に対価が支払われる世界線
ここまで見てきたことを押さえた上で、もしすべての看護ケアに対価が支払われたとしたら、どのような社会となるでしょうか?
まず、本来専門職として必要だと判断されたケアであっても、診療報酬の枠組みに組み込まれていなかった場合、患者の実費払いで実施するか、メニューにないので実施しない、という2つの選択になります。
具体的な例で言うと、落屑が著しいAさんに入浴や洗髪といったケアを週に何度もしたい、と考えた場合、Aさんに適用される診療報酬のメニュー上週に3回まで、となっていたとします。その場合、患者さんから実費を支払ってもらって実施するか、実施を見送るかということになります。専門職としてアセスメントした結果必要だと判断したにも関わらず、です。
また、行うケアに対し賃金が発生するのであれば、当然ながら説明と同意が不可欠です(賃金が発生しなくても必要ですが、実施した後で「実はお金がかかります」はできないですよね)。その際、経済的に厳しい患者さんが「お金がないので不要です」と拒否する可能性があります。「患者さんにお金がないから実施しませんでした」は専門職としての態度としては不適切です。
すべての看護ケアに対価が必要となる場合、すべての看護ケアに対しこのようなプロセスが必要となるのです。
包括的な報酬制度だからこそ力が発揮される看護ケア
上記のような問題を考えると、ある程度包括的に報酬枠組みがあった方が、実は看護職にとっても都合が良いという見方もできます。
いちいち対価のことを気にしなくて良いので、入浴や洗髪が通常以上に必要だと判断したときにすぐに実施できますし、僕たちの権限の範囲で自由にアセスメントしてケアを届けられるのです。
ただ、だからといってこうした細やかなケアを評価しなくて良い、ということではありません。これまでの診療報酬改定の歴史を見てみると、行われたケアが患者のアウトカムに明確につながったというエビデンスが確認できれば、そのケアは診療報酬の加算等としてきちんと評価されます。
つまり、僕たちが日常行っているケアが、患者さんの状態を良くすることが、客観的かつ数値的なエビデンスとして明らかにすることができれば、そのケアが診療報酬に組み込まれるということもあり得るのです。
患者さんの主観的ではない客観的な状態が良くなるというこうしたケアの有効性を示していくことも、研究活動として重要なことのひとつなのです。僕たち研究者は、なかなかこのようなデータにアクセスすることが難しい現状ではありますが、臨床の方々とうまく協働して、僕たちのケアのエビデンスを確立していく将来が来ると良いなと願っています。